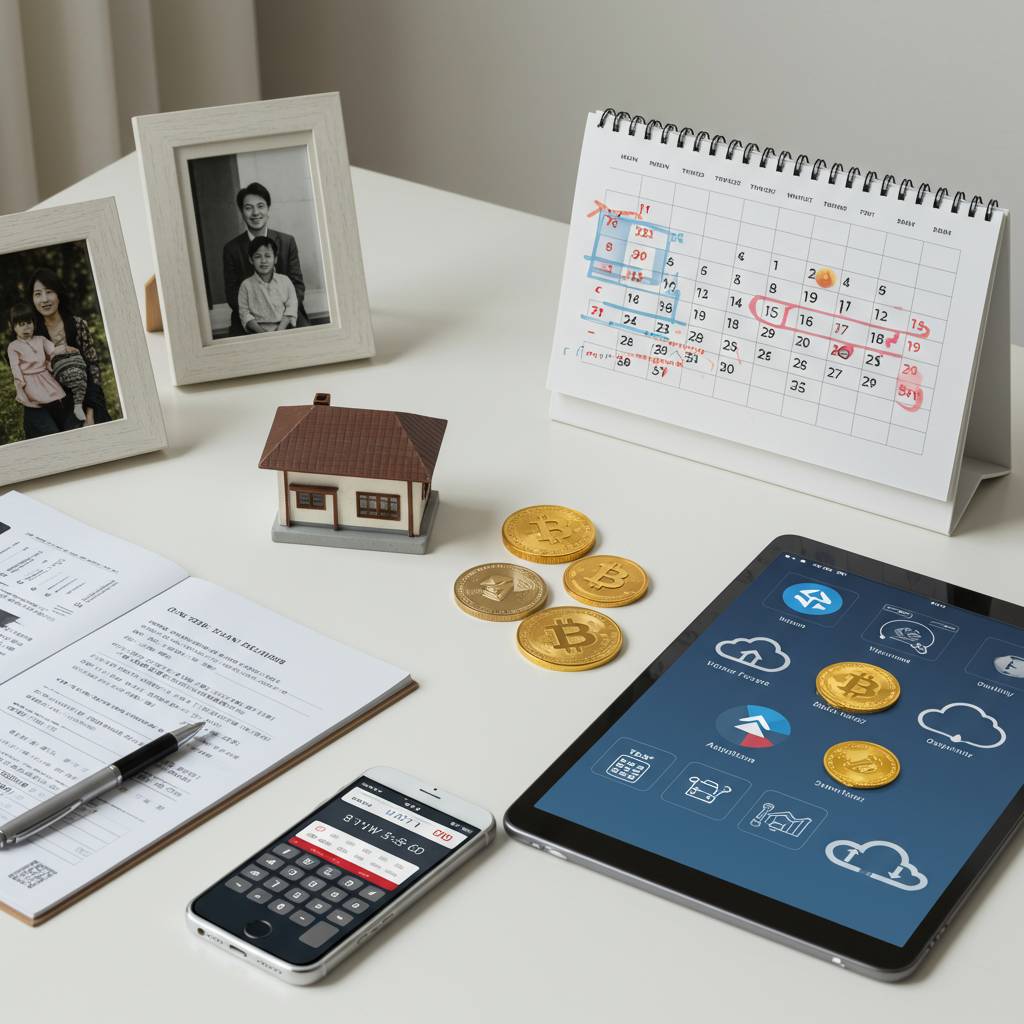
みなさん、相続対策というと不動産や預貯金、株式などの従来型資産をイメージしませんか?でも令和の時代、ビットコインやNFT、さらにはSNSアカウントまで、デジタル資産の価値が急上昇しています。
国税庁の調査によると、日本国内の仮想通貨保有者は約300万人を超え、その資産価値は年々増加傾向にあるんです。にもかかわらず、デジタル資産の相続対策をしている方はわずか5%程度という調査結果も…。
「仮想通貨やデジタルデータも相続財産になるの?」
「親のLINEアカウントやAmazonアカウントはどうすればいい?」
「税務署はデジタル資産をどう評価するの?」
こんな疑問をお持ちの方も多いはず。実は最近、デジタル資産の相続トラブルが急増しているんです。
この記事では、見落としがちなデジタル資産の相続税対策について、最新の税制情報と具体的な対策法をお伝えします。令和時代に備えるべき新しい相続対策、ぜひ最後までご覧ください!
1. 相続税にデジタル資産も対象に?知らないと損する令和の新常識
相続税の対象となる財産には、現金や不動産、有価証券などの従来型資産が含まれることは広く知られています。しかし、令和の時代に入り、新たに注目すべきはデジタル資産の存在です。仮想通貨やNFT、各種ポイント、オンラインゲーム内の資産など、目に見えない形の財産が急増しています。これらのデジタル資産も相続税の対象となるのをご存知でしょうか?
例えば、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨は、相続税の計算においては、亡くなった日の時価で評価されます。国税庁も「暗号資産(仮想通貨)と相続税」についての見解を明確に示しており、無視できない資産として認識されています。
さらに注目すべきは、デジタル資産の把握の難しさです。故人がどのような仮想通貨を保有していたか、どこの取引所で管理していたのか、アクセス情報はどうなっているのかなど、遺族が知らないケースが多発しています。そのため、生前からのデジタル資産管理と情報共有が極めて重要です。
また、デジタル遺品という観点からも考える必要があります。SNSアカウントやクラウドサービス上の写真・動画、電子書籍など、金銭的価値だけでなく思い出としての価値も持つデジタルコンテンツをどう引き継ぐかも検討すべき課題です。
相続税の専門家である税理士の佐藤氏は「デジタル資産は目に見えないため、相続の際に見落とされやすい。しかし税務署はデータ照会などで把握できるケースも増えているため、申告漏れには注意が必要」と指摘しています。
令和時代の相続税対策では、従来の不動産や金融資産だけでなく、デジタル資産も含めた総合的な対策が必要不可欠です。早めに専門家に相談し、デジタル資産も含めた相続対策を進めることをお勧めします。
2. 仮想通貨やNFTも相続税の対象!デジタル時代の資産引き継ぎ方法
デジタル資産の普及に伴い、相続の風景も大きく変わりつつあります。かつては現金や不動産、株式といった従来型の資産が相続の中心でしたが、今やビットコインをはじめとする仮想通貨やNFT(非代替性トークン)も重要な相続対象となっています。国税庁の見解では、これらのデジタル資産も相続税の課税対象であることが明確に示されています。
仮想通貨の相続では、まず正確な評価額の算出が課題となります。相続税における仮想通貨の評価は、原則として相続開始時点での市場価格が基準となります。しかし、仮想通貨市場は変動が激しいため、相続手続きの間に価値が大きく変わることも少なくありません。また、取引所ごとに価格差があるケースもあるため、どの取引所の価格を参照するかも問題となります。
さらに深刻なのが、暗号資産へのアクセス方法の引き継ぎです。秘密鍵やパスワードが不明になると、いくら法的に相続権があっても資産にアクセスできなくなります。日本では既に、秘密鍵がわからず莫大な仮想通貨資産にアクセスできなくなった相続事例が報告されています。
NFTについても同様の問題があります。デジタルアートや収集品としての価値を持つNFTは、市場価値の評価が難しく、また所有権の移転方法も従来の資産とは異なります。MetaMaskなどのウォレットの管理情報も含めた包括的な相続計画が必要です。
対策としては、まず「デジタル遺言」の作成が効果的です。これは法的な遺言書とは別に、デジタル資産へのアクセス方法や管理情報をまとめたものです。セキュリティに配慮しながら、信頼できる相続人や弁護士に情報を託す方法が一般的です。大手取引所のCoincheckやbitFlyerなどでは、相続手続きのガイドラインを設けていますが、取引所に預けていない資産については別途対策が必要です。
また、家族信託や民事信託を活用する方法も注目されています。デジタル資産の管理を信託することで、相続発生時のスムーズな資産移転が可能になります。特に認知症リスクがある高齢者のデジタル資産管理には有効な手段といえるでしょう。
デジタル資産の相続対策は、従来の相続計画に新たな視点を加える必要があります。専門知識を持った税理士や弁護士との相談を通じて、包括的な相続戦略を立てることが重要です。デジタル時代の資産を次世代に確実に引き継ぐための準備を、今から始めておきましょう。
3. 親のSNSアカウントどうする?デジタル遺品も含めた相続対策のポイント
近年、親世代のSNS利用が増え、「デジタル遺品」の問題が注目されています。故人のSNSアカウントやネットサービスの契約は、財産や思い出として大切なものですが、相続手続きが複雑なケースが多いのが現状です。
まず重要なのは、生前にデジタル資産の整理をしておくことです。各SNS(Facebook、Twitter、Instagram等)やApple ID、Googleアカウントなどの情報を一覧にし、家族に伝えておくと安心です。特にパスワード管理アプリ「LastPass」や「1Password」などを活用すれば、セキュリティを保ちながら情報を整理できます。
各サービスの死後対応ポリシーも把握しておきましょう。Facebookは「追悼アカウント」設定があり、指定した追悼管理人がアカウントを管理できます。Googleは「アカウント無効化管理ツール」で、一定期間利用がない場合の対応を事前設定できるのが特徴です。
デジタル遺品整理を専門とする「デジタル相続サービス」も登場しています。株式会社デジタル遺品整理や、Yahoo! JAPANの「エンディングノートサービス」などが代表例で、専門家のサポートを受けられます。
写真や動画のクラウドストレージも重要な資産です。Google フォトやiCloudなどに保存された思い出の写真は、アカウント情報がないとアクセスできなくなるため注意が必要です。家族写真は定期的にバックアップを取り、物理的なメディアにも保存しておくと安心です。
相続税の観点では、仮想通貨やNFTなどのデジタル資産は評価対象となります。これらの資産情報も含めた「デジタル版エンディングノート」を作成しておくことで、遺族の負担を減らし、円滑な相続手続きが可能になります。
4. 令和版相続税対策、見落としがちなデジタル資産の評価方法
相続税対策を考える際、不動産や金融資産に目が行きがちですが、現代ではデジタル資産の取り扱いも重要な検討事項となっています。暗号資産(仮想通貨)、NFT、デジタルコンテンツなど、形のない資産も相続財産として評価対象です。
暗号資産の評価方法は、原則として相続開始時における取引価格で評価します。ビットコインやイーサリアムなど主要な暗号資産は、国税庁が発表する評価方法に従い、相続開始時の時価(取引所の価格)で計算します。複数の取引所で価格差がある場合は、国内主要取引所の平均価格が用いられることが一般的です。
NFT(非代替性トークン)の評価は複雑です。デジタルアートや希少性の高いコレクション品としての性質を持つNFTは、取得価格や直近の取引価格を基準とすることが多いですが、明確な評価基準がまだ確立されていません。専門家による鑑定評価が必要になるケースもあります。
オンラインサービスのアカウントも見落としがちな資産です。Apple ID、Google、Amazonなどに紐づく購入済みのデジタルコンテンツ(音楽、映画、電子書籍など)やポイント、マイレージも価値を持ちます。サブスクリプションサービスの契約状況も確認し、必要に応じて解約手続きを検討するべきでしょう。
デジタル資産の相続手続きの難しさは、資産へのアクセス権の問題です。パスワードやシードフレーズなどの管理方法を家族に伝えておかないと、資産価値があっても相続人がアクセスできないという事態に陥ります。デジタル遺言サービスやパスワード管理ツールの活用、公証人を介した秘密証書遺言の作成なども検討すべき選択肢です。
税務申告の際には、デジタル資産の存在と評価額を正確に申告することが重要です。過少申告とならないよう、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。税理士法人フォーサイトや相続税に強い税理士事務所などでは、デジタル資産の評価・申告についても相談に応じています。
これからの相続税対策では、従来の不動産や金融資産だけでなく、デジタル資産も含めた総合的な対策が必要です。専門家と連携しながら、時代に合った相続対策を進めていきましょう。
5. 税務署も注目!増加するデジタル資産と相続税申告の新たな課題
ビットコインやNFTなど、デジタル資産の価値が高騰する中、税務署の視線も厳しさを増しています。実際、国税庁はデジタル資産専門の調査チームを結成し、申告漏れの発見に力を入れているのです。ある事例では、被相続人が所有していたビットコインが申告されず、後日の税務調査で約2,000万円の追徴課税が発生したケースもあります。
デジタル資産の相続で特に難しいのが「把握」と「評価」です。仮想通貨取引所の口座情報、暗号資産のウォレット、各種オンラインサービスのアカウントなど、被相続人がどのようなデジタル資産を持っていたかを遺族が知らないことも少なくありません。
評価方法については、国税庁の通達によれば、仮想通貨は相続発生時の時価で評価することが原則です。しかし、価格変動が激しい特性から、「相続開始の時における課税時期から一定期間前後の価格の平均値」を用いる場合もあります。
東京国際会計事務所の税理士、山本誠一氏は「デジタル資産の相続対策では、資産リストの作成と定期的な更新、パスワード管理方法の共有が不可欠」と指摘します。
相続税申告の際は、デジタル資産の評価根拠を明確に示す資料の準備も重要です。取引所が発行する残高証明書や、評価時点での相場を示す資料などを添付することで、税務署とのトラブルを未然に防ぐことができます。
デジタル資産は「形がない」からこそ、事前の対策と正確な情報共有が重要になるのです。適切な相続税申告のためにも、専門家と連携しながら、新しい資産形態に対応した相続対策を進めましょう。
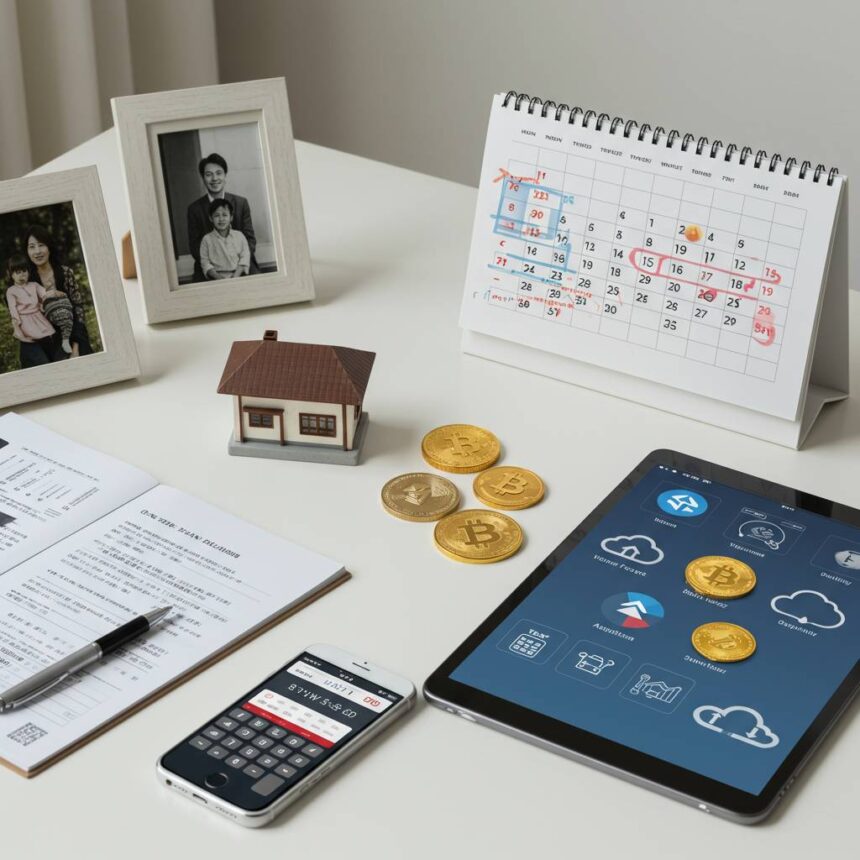





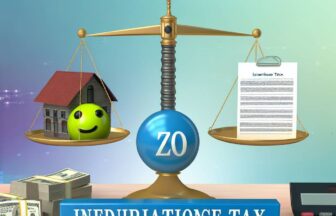








この記事へのコメントはありません。