
相続税の基礎控除が2027年に変わるって聞いてますか?「まだ先のこと」なんて思っていると、あっという間に期限が迫ってきますよ!実は今から準備しておかないと、将来大きく損をしてしまう可能性があるんです。
相続税の基礎控除が引き下げられると、これまで相続税の心配がなかった方も課税対象になるかもしれません。特に不動産や預貯金をお持ちの方は要注意です。でも大丈夫、今からできる対策はたくさんあります!
この記事では、税理士として多くの相続案件を扱ってきた経験から、基礎控除減額に備えた具体的な対策方法をご紹介します。生前贈与の活用法や不動産の有効活用、相続税評価を下げるテクニックなど、今すぐ始められる方法を分かりやすく解説していきますね。
相続対策は早めに始めるほど選択肢が広がります。2027年の改正に備えて、今から一緒に賢い資産管理の方法を学んでいきましょう!
1. 2027年が迫る!相続税基礎控除減額で損しない方法、今すぐできることは?
相続税の基礎控除が2027年に大幅減額されることが決定しました。これまで「3000万円+600万円×法定相続人数」だった基礎控除が「1800万円+400万円×法定相続人数」へと引き下げられます。この変更により、これまで相続税の対象外だった多くの方が新たに課税対象となる可能性が高まっています。基礎控除の縮小で相続税の課税対象者は約1.5倍に増加すると試算されており、早めの対策が不可欠です。
まず押さえておきたいのが、生前贈与の活用です。年間110万円までの基礎控除を利用した計画的な贈与を行うことで、将来の相続財産を減らすことができます。特に教育資金の一括贈与制度や結婚・子育て資金の一括贈与制度など、特例を利用した贈与も検討価値があります。
また、不動産の有効活用も重要な対策のひとつです。アパートやマンションなどの収益物件に投資することで、相続税評価額の圧縮が可能になります。賃貸不動産は時価よりも低く評価される傾向があるため、税制上のメリットが期待できるのです。
生命保険の活用も見逃せません。生命保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。この非課税枠を活用することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
さらに、今のうちに専門家への相談を検討しましょう。税理士や弁護士など相続の専門家と連携し、自分の資産状況に合わせた最適な対策を立てることが重要です。三井住友信託銀行や野村證券などの金融機関でも相続対策のコンサルティングサービスを提供しています。
相続税の基礎控除減額まであと数年です。今から対策を始めることで、将来の相続税負担を大きく軽減できる可能性があります。早めの行動が、家族の未来を守る第一歩となるでしょう。
2. 【専門家が解説】相続税の基礎控除が下がる前にやるべき5つのこと
相続税の基礎控除の引き下げが検討されており、多くの方が今後の資産対策に不安を感じています。これまで相続税の対象外だった方も、改正後は納税義務が発生する可能性が高まっています。そこで税理士として多くの相続案件を手がけてきた経験から、基礎控除が下がる前に実施すべき5つの対策をご紹介します。
1. 財産の棚卸しと評価を行う
まずは自分の財産を正確に把握することが重要です。不動産、預貯金、有価証券、生命保険、事業用資産など、すべての財産を洗い出し、相続税評価額を試算しましょう。特に不動産は路線価や倍率方式で評価するため、実勢価格とは異なります。東京国税局や各税務署のホームページで路線価図を確認するか、税理士に相談して正確な評価額を把握しましょう。
2. 生前贈与の活用
年間110万円までの基礎控除を活用した計画的な生前贈与は、相続税対策の基本です。さらに教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与など、特例制度も活用できます。ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるため、早めの行動が肝心です。
3. 不動産の有効活用
賃貸アパートやマンションなどの建設により、土地の評価額を下げる小規模宅地等の特例を活用する方法があります。居住用や事業用の土地は最大80%の評価減が可能です。また、不動産を法人化することで、自社株対策と組み合わせた節税も検討できます。
4. 生命保険の活用
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。例えば配偶者と子2人の場合、1,500万円まで非課税となります。保険の契約者と被保険者、受取人の関係を適切に設定することで、相続税の負担を軽減できます。
5. 相続税の納税資金対策
相続税は現金で納付するのが原則です。不動産が多い場合、納税資金が不足して不動産を売却せざるを得ないケースもあります。相続税の納税資金を確保するため、終身保険や個人年金保険などの活用を検討しましょう。また、延納制度や物納制度についても理解しておくことが重要です。
これらの対策は早めに着手するほど効果的です。大和総研の調査によれば、基礎控除の引き下げにより相続税の課税対象者は約1.5倍に増加すると予測されています。まずは税理士や弁護士などの専門家に相談し、自分の資産状況に合わせた最適な対策を立てることをお勧めします。
3. 相続税の節税チャンス終了間近!今からでも間に合う対策術
相続税の基礎控除見直しが進められる中、現行制度下での節税対策はまさに「今」が勝負です。税制改正により、これまで活用できていた優遇措置が縮小される可能性が高まっています。特に注目すべきは小規模宅地等の特例です。この特例を活用すれば、自宅の敷地など条件を満たす土地は最大80%評価減が可能になります。例えば5,000万円の土地であれば、評価額を1,000万円まで下げられるケースも。また、生前贈与の非課税枠の活用も重要です。暦年贈与では年間110万円まで非課税で贈与できるため、計画的に実行すれば大きな節税効果が期待できます。教育資金の一括贈与制度も見逃せません。1,500万円まで非課税で孫などへ教育資金を贈与できる制度ですが、この優遇措置も見直しの対象となる可能性があります。さらに、家族信託の活用も検討価値があります。認知症などで判断能力が低下した場合でも、あらかじめ信頼できる家族に財産管理を託しておくことで、相続対策と資産防衛の両立が可能です。相続税対策は早めの準備が肝心です。専門家のアドバイスを受けながら、現行制度の利点を最大限に活用しましょう。
4. 知らないと損する!相続税基礎控除変更で影響を受ける人の特徴と対処法
相続税の基礎控除額の変更は、多くの方に影響を及ぼす可能性があります。特に以下のような特徴を持つ方々は、早めの対策が必要となるでしょう。
まず、都市部の不動産を所有している方です。東京、大阪、名古屋などの都市部では地価が高く、マンション一室や小さな土地でも相続税の課税対象になりやすくなります。特に東京23区内の不動産は評価額が高いため、基礎控除の引き下げにより新たに課税対象となる可能性が高まります。
次に、事業用資産を多く持つ中小企業のオーナーも要注意です。事業承継税制の適用を受けられる場合もありますが、要件が厳しく、適用漏れが生じるケースも少なくありません。基礎控除の変更により、これまで課税対象外だった事業用資産が課税対象となる可能性があります。
また、金融資産を多く保有している方も影響を受けやすいでしょう。預貯金、投資信託、株式などの金融資産は換金性が高く、相続税評価も比較的シンプルです。基礎控除の引き下げにより、金融資産だけで基礎控除を超える方が増加する見込みです。
これらの方々は、以下の対処法を検討すべきでしょう。
1. 生前贈与の活用: 年間110万円までの基礎控除を利用した計画的な生前贈与を行うことで、相続財産を減らすことができます。教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与の特例も有効です。
2. 不動産の有効活用: 賃貸アパートなどに転換することで、不動産の評価額を下げられる可能性があります。小規模宅地等の特例も検討しましょう。
3. 生命保険の活用: 生命保険金には非課税枠があるため、相続対策として効果的です。被相続人が保険料を負担し、受取人を相続人にすることで、相続財産を効率的に移転できます。
4. 信託の活用: 家族信託や民事信託を活用することで、財産管理と円滑な承継を同時に実現できる可能性があります。
基礎控除変更による影響を最小限に抑えるためには、税理士や弁護士などの専門家に早めに相談することをお勧めします。藤井会計事務所や相続あんしん相談センターなどの専門機関では、個別の状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができます。相続税対策は時間をかけて計画的に進めることが重要なため、変更が実施される前に早めの行動が賢明です。
5. 相続税改正でピンチをチャンスに!今から始める賢い資産移転のコツ
相続税の基礎控除見直しがいよいよ現実味を帯びてきました。これまで「3,000万円+600万円×法定相続人数」という基礎控除額が引き下げられる可能性が高まっています。この改正は多くの方にとって税負担増となりますが、適切な準備をすれば、むしろ資産を守るチャンスにもなります。
まず注目したいのが「生前贈与の活用」です。年間110万円の基礎控除を利用した計画的な贈与は、相続財産を減らす効果的な方法です。特に教育資金の一括贈与制度では、孫などへの教育資金として最大1,500万円まで非課税で贈与できます。この制度は延長される可能性もありますが、確実に活用するなら今のうちに検討すべきでしょう。
次に「不動産の有効活用」も重要なポイントです。自宅の敷地を活用したアパート経営などは、相続税評価額を下げられる可能性があります。ただし、単に相続税対策だけでなく、収益性も考慮した判断が必要です。日本財託や大京などの不動産会社に相談すると、資産状況に合わせた提案を受けられます。
また「保険の活用」も見逃せません。生命保険の死亡保険金は、「500万円×法定相続人数」までが非課税となります。この非課税枠を活用すれば、相続税の負担を軽減できるでしょう。
さらに「家族信託」という選択肢も検討価値があります。認知症などで判断能力が低下した場合のリスク対策として、また柔軟な資産承継の手段として注目されています。
どの対策も早めに始めることが重要です。税理士などの専門家に相談し、自分の資産状況に合った最適な方法を選びましょう。東京税理士会や日本税理士会連合会のホームページでは、地域の税理士を検索できます。
相続税改正はピンチではなく、家族の将来について考え、より良い資産承継を実現するチャンスです。今から準備を始めることで、大切な資産を次世代に確実に引き継ぐことができるでしょう。



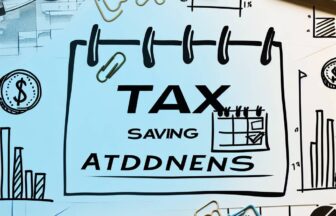


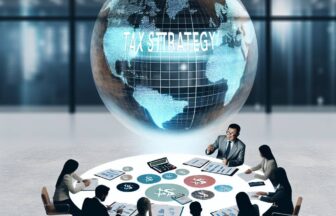

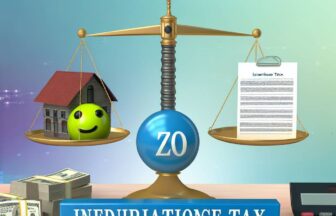






この記事へのコメントはありません。